花屋を経営していると、
「スタッフを募集しても応募が来ない…」
という悩みを抱えるオーナーさんも多いのではないでしょうか。
昔は店先に「スタッフ募集:要普免(要普通免許)」と小さく貼り紙を出すだけで履歴書を持ってきてくれる応募者がたくさんいた時代もあったそうです。
小学生の女の子のなりたい職業ランキングで「お花屋さん」が常に上位に入るほど、花屋は憧れの仕事でした。
ところが近年では状況が変わり、**花屋の求人(「花屋 求人」)**は簡単には集まらなくなっています。
実際、2000年代後半頃から花屋で働きたい人が減ってきたという声もあります。
花ブームから20年ほど経ち、「思ったより大変な仕事」「好きなだけでは続けられない」「趣味にする方が楽しい」といった現実的な情報が広まったことが背景にあるようです。

花屋の仕事は見た目の華やかさとは裏腹に、重い荷物を運んだり早朝の市場に仕入れに行ったりと肉体労働の側面があり、休日も母の日やイベント時期は忙しくなりがちです。
また給与面でも他業種に比べ高いとは言えず、東京都内でも時給は800~900円程度(最低賃金レベル)で、正社員でも月給18万円程度といわれます。
こうした条件面の厳しさも、人材確保を難しくしている理由でしょう。さらに、フラワー業界全体でも人手不足と小規模店の閉店増加が指摘されています。
店舗運営に必要なスタッフが確保できず、経営維持が難しいケースが増えているのです。一方で消費者の購買行動も変化し、オンラインショップや定期便サービスなど新しい市場も生まれています。
このように業界環境が変わる中、優秀な人材を採用することが以前にも増して重要になっています。
では、花屋の求職者はどのように仕事を探しているのでしょうか?そしてオーナーはどうすれば効果的に求人できるのでしょうか。ここから具体的な方法と戦略を見ていきましょう。
求職者は花屋の求人をどこで探している?

まず、求職者が花屋の求人情報を探す方法を押さえておきましょう。
人材を採用するには、求職者の目に留まる場所に求人情報を載せることが大切です。
最近の求職者は主に以下のような手段で花屋の仕事を探しています。
- 求人サイト・求人アプリ: スマホやパソコンから手軽に検索できる求人サイトは、最も一般的な探し方です。例えばIndeedやタウンワーク、リクナビNEXTなど大手サイトでは「花屋」の求人募集が数多く掲載されています。
実際、Indeedで「花屋」の求人を検索すると常時1000件以上ヒットすることもあり、多くの求職者がこれらのサイトで条件に合う花屋の仕事を探しています。正社員希望の人は転職サイト、アルバイト希望の人はアルバイト専門サイトなど、自分の希望に合わせて使い分けています。 - 花業界専門の求人サイト: 花屋やフラワー業界に特化した求人サイトも存在します。例えば「花JOB」や「フラワージョブ」といったサイトでは、エリアや職種、雇用形態で絞り込んで花関係の求人情報を探すことができます。花屋で働きたい熱意のある人はこうした専門サイトもチェックするので、掲載する側としても活用したいところです。
- SNS(ソーシャルメディア): 若い世代を中心に、SNSで求人情報を目にするケースも増えています。例えば、お店のInstagramやTwitterで「スタッフ募集」の告知を見て応募するパターンです。花屋さんの場合、日頃からSNSでお店の花やディスプレイの写真を発信してファンを作っているところも多いですよね。
そうしたフォロワーの中には「このお店で働いてみたい!」という人もいるため、SNSで求人告知をするのは効果的です。ハッシュタグで**#花屋求人や#スタッフ募集**と付けて投稿すれば、興味のある人の目に留まりやすくなります。 - 求人誌・フリーペーパー: 駅や商業施設で配布されている無料の求人情報誌(例えば「タウンワーク」などのフリーペーパー)も、今でも一定の効果があります。地域密着の求人誌であれば近隣で働きたい人の目に留まります。ネットに慣れていない層や、通勤途中にパラパラと探したい人などには有効です。
- ハローワーク(公共職業安定所): 国の運営するハローワークでも花屋の求人募集が出ていることがあります。登録求職者は定期的にチェックしていますし、シニア層などネットを使わない方にもリーチできます。
ただしお店によってはハローワークに求人を出す際、店名や所在地を非公開にしていることもあります(応募が殺到するのを防ぐため等)。その場合、求職者は直接ハローワークの窓口で詳細を聞かないと応募できない仕組みです。
ハローワークに載せる際は、情報公開範囲も設定できることを覚えておきましょう。 - 直接アプローチ(店頭掲示・問い合わせ): 求職者の中には「このお店で働きたい」と具体的に憧れのショップを決めている人もいます。
そういった方はお客さんとしてお店に足を運び、店頭にスタッフ募集の貼り紙が出ていないか確認したり、思い切って店員さんに「求人募集していますか?」と尋ねたりします。
実は花屋は常に人手不足になりがちで、小さいお店ほど求人広告を出さずに人を探しているケースも多いです。
そのため貼り紙がなくても質問されれば「ちょうど募集しようと思っていたんだよ」と話が進むこともあります。このように店頭での掲示や直接問い合わせも、熱意ある求職者にとっては立派な探し方なのです。 - 専門学校・スクール経由: フラワーデザインや園芸の専門学校、スクールに通っている人が就職先を探す場合、学校の就職支援や講師の紹介で花屋の求人情報を得ることがあります。
オーナー側から見ると、そういった学校に求人票を出したりインターンを受け入れたりすることで、将来の人材を確保するチャンスになります。
求職者も「卒業生が働いているお店」など安心感を持てる紹介だと応募に踏み切りやすいでしょう。 - 人脈・紹介: 花業界は横のつながりが強い業界です。他店同士の交流もあり、「〇〇さんの花屋で求人してるらしいよ」と情報が回ることもあります。花屋でアルバイト経験のある知人が別の花屋を紹介してくれる、といったケースもあるでしょう。とくに経験者を紹介してもらえる場合、最初から基本的なスキルがある即戦力を採用できる利点もあります。
- 派遣サービスの利用: 実はお花の仕事に特化した派遣会社も存在します。フラワーショップ専用の人材派遣サービスでは、経験者はもちろん未経験者でも働きやすいようマッチングしてくれます。
派遣スタッフとして短期でお試し勤務し、そのまま気に入れば長期採用…という流れも可能です。
求職者側から見ると応募から採用までスピーディーに進むメリットがあります。
オーナー側も、急な欠員時など派遣スタッフで凌ぎつつ採用活動を行うという手も考えられます。
以上のように、「花屋の求人」を探す手段は多岐にわたることがわかります。
オーナーとしては、これら求職者の動向を踏まえて求人情報を発信していく必要があります。
次の章では、オンラインとオフラインそれぞれで効果的な求人掲載方法を見ていきましょう。
効果的な求人掲載方法:オンライン vs. オフライン
求人募集を成功させるには、オンライン媒体とオフライン媒体の両方を上手に活用するのがポイントです。それぞれにメリット・デメリットがありますので、バランス良く組み合わせて貴店に合った採用活動を行いましょう。
ここではオンラインとオフラインそれぞれの効果的な求人方法とコツを解説します。
オンラインでの求人掲載のコツ

近年、求人と言えばオンラインが主流です。スマホひとつで検索・応募が完結する手軽さから、求職者の大半はインターネット経由で仕事探しをしています。
花屋のオーナーにとっても、オンライン求人は幅広い層にアプローチできる強力な手段です。以下に効果的なポイントをまとめます。
- 主要な求人サイトに掲載する: まずはIndeedや求人ボックス、ジモティーなど無料で掲載できる大手求人サイトに情報を載せましょう。
無料掲載でも十分応募が見込めますし、有料オプションを使えば上位表示されて露出が増えます。実際、ある老舗花屋ではリクルート社のサービスを通じてIndeedに求人を掲載したところ、2週間で8名もの応募があり、その中から正社員2名・パート2名を採用できたそうです。
しかも費用は7,000円程度と非常に低コストで済み、採用コストパフォーマンスの高さに驚いたといいます。このように大手求人サイトは利用者が多いため、短期間で多数の応募者を集めやすいのが魅力です。 - 花業界に特化したサイトも活用: 前述のように花屋専門の求人サイト(花JOB等)もあります。花屋志望の熱意ある人が集まる分、応募者のモチベーションが高い傾向があります。
「花に囲まれて働きたい」「フラワーアレンジメントのスキルを活かしたい」といった明確な意欲を持つ人材にリーチできるでしょう。
実際、宮崎県のある花屋では「生花の技術を身につけたい」という若手応募者たちに出会い、採用に成功しています。
専門サイトへの掲載や業界向けSNSコミュニティでの情報共有によって、花が好きで技術を学びたい層に求人情報を届けることができます。 - 自社のホームページやSNSで発信: お店のホームページを持っている場合は、採用情報のページを作成しましょう。「スタッフ募集」の告知を載せておくだけでも、熱心に探している人が見つけてくれる可能性があります。
またInstagramやTwitter、Facebookなどお店が運用しているSNSアカウントでも求人告知を行いましょう。お店のファンや地元の人がシェアしてくれれば拡散効果も期待できます。
SNS投稿ではお店の雰囲気やスタッフの笑顔、仕事風景など写真付きで紹介すると「ここで働きたい!」とイメージしてもらいやすくなります。
募集要項へのリンクを貼ったり、問い合わせ方法を明記したりして、興味を持った人がすぐ行動できるようにしましょう。 - 魅力的な求人内容を作る: オンライン掲載では文章で仕事の魅力を伝える必要があります。
求人タイトルやキャッチコピーには「未経験OK」「週○日から勤務可」「社員割引あり」など求職者が惹かれるキーワードを入れると効果的です。
仕事内容の説明では、単に業務リストを書くのではなく「お客様の記念日をお花で彩るやりがいのあるお仕事です」などポジティブなやりがいも伝えましょう。
特に若い世代は仕事の意義や雰囲気を重視するので、職場の魅力や学べることを具体的に書くのがおすすめです。「未経験でも先輩が基本から教えます」「季節ごとのイベント装花に携われます」など、ワクワクする要素を盛り込みましょう。 - 応募しやすい工夫: オンライン応募は気軽とはいえ、応募フォームが煩雑だったりレスポンスが遅かったりすると機会損失に繋がります。
応募が来たらすぐに連絡を取り、面接日程を調整しましょう。メールだけでなく必要に応じて電話やSNSのDMで連絡するなど、スピーディーな対応を心がけます。
「興味はあるけど応募しようか迷っている」という人向けに、見学OKや質問歓迎の旨を求人情報に記載しておくのも良いでしょう。
応募のハードルを下げることで、母集団(応募者数)を増やすことに繋がります。
オフラインでの求人掲載のコツ

オンライン全盛の時代とはいえ、オフラインの求人手法も依然として有効です。特に地域密着型の花屋さんでは、地元の人材をオフラインで掘り起こすことで良いご縁が生まれることがあります。以下にオフライン求人のポイントを挙げます。
- 店頭での「スタッフ募集」掲示: 自店舗で求人を出す基本中の基本は、店頭ポスターや張り紙によるスタッフ募集の告知です。
お店の前を通る地元の方や、お客様として来店した方の目に留まれば、そのまま応募に繋がる可能性があります。貼り紙を出す際は、手書きでも構いませんが目立つデザインにする、営業時間外でも見える位置に貼る、といった工夫をしましょう。
以前ほど貼り紙だけで応募が殺到する時代ではないものの、「地元で花屋の仕事を探していた!」という人に刺されば効果は絶大です。
実際かつては貼り紙だけで十分応募が集まったという話もあるくらいです。現在でも基本的な方法として忘れず実践したいところです。 - 知人・お客様からの紹介: 地域に根差した花屋さんほど、口コミや紹介で良い人材に出会えることがあります。
常連のお客様でお花が好きな方に「どなたか紹介してもらえませんか」と声をかけてみたり、知り合いの経営者仲間に人を探している旨を伝えたりしてみましょう。花業界は横のつながりが強いので、
他店のオーナー仲間から「うちには応募が来すぎて採用しきれなかった人がいるんだけど紹介しようか?」なんて情報をもらえることもあります。
従業員がいる場合は従業員の友人知人ネットワークも頼ってみましょう。「友達で花が好きな子がいる」という話が出てきたらしめたものです。紹介であれば人柄もある程度わかった上で面接できるので安心感もあります。 - 地元の学校や団体と連携: 地域の高校や専門学校、フラワーアレンジ教室などに求人情報を置かせてもらうのも一つの手です。
特に園芸科のある高校や、フラワーデザインの専門学校では、卒業後に花業界への就職を希望する生徒も多いはずです。学校の就職担当や講師に相談し、求人チラシを掲示板に貼ってもらったり、生徒に紹介してもらえないか働きかけてみましょう。
「地元の花屋に就職」というのは学生さんにとってもイメージしやすく、応募に繋がりやすいです。 - ハローワークや求人誌への掲載: 公共のハローワークや地域の求人情報誌に掲載する方法も、オフラインでは王道です。
ハローワークは掲載費無料で幅広い年齢層に情報が行き渡ります。求人誌は発行スケジュールに合わせて掲載依頼をする必要がありますが、紙媒体で目に留まることでネットをあまり見ない層にもリーチできます。
特に中高年のパート希望者などはハローワークや新聞折込の求人欄をチェックしていることがあります。店舗がある地域の特性に応じて、これらオフライン媒体も併用しましょう。 - 面接前の見学歓迎: オフラインで声をかけてきてくれた求職者に対しては、いきなり面接ではなく職場見学や職場体験を提案してみるのもオススメです。
短時間お店を手伝ってもらいお互い雰囲気を確認することで、ミスマッチを防ぐ効果があります。「百聞は一見に如かず」で、写真や文章では伝えきれないお店の魅力を実感してもらえるでしょう。
これは厳密には求人掲載方法ではありませんが、オフラインならではのアナログなアプローチとして覚えておいて損はありません。
オンラインとオフライン、それぞれ単体でも効果はありますが、組み合わせて相乗効果を狙うのが今の時代の採用成功のカギです。
例えば「店頭貼り紙 + SNS告知」で地元とネット両方にアプローチしたり、「求人サイト掲載 + 専門学校にも情報提供」で幅広い世代にリーチしたりと、複数チャネル戦略でいきましょう。
成功事例と花屋求人のおすすめ戦略

最後に、実際の成功事例を踏まえつつ、花屋の求人募集を成功させるための具体的な戦略ポイントを整理します。
オンライン活用で人材確保に成功した事例
宮崎県で60年以上続く老舗フラワーショップ「岡田花店」さんの事例をご紹介します。
同店ではブライダルフラワーを任せていたスタッフが退職することになり、急遽後任を採用しなければならない状況に陥りました。
従来通りまず1ヶ月間求人募集をかけてみたものの、応募者は予想より少なく、来ても必要なスキルを満たさない人ばかり…。オーナーはかなり焦り、「このままではブライダル事業を継続できない、最悪場合によっては規模縮小も検討しなければ」と危機感を抱いたそうです。
まさに今の人手不足時代を痛感する体験ですよね。
打つ手がなくなった岡田花店さんは、リクルート社に相談して紹介された採用支援ツール「Airワーク採用管理」を試してみることにしました。このツールを使って求人情報を作成し、Indeedの有料枠(Indeed PLUS)にも掲載したところ、なんと2週間で8件もの応募が集まったのです。
しかも応募者は全員20代の若手で、「生花の技術を身につけたい」「地元で花の仕事がしたい」といった明確な志望動機と高いモチベーションを持った人たちでした。
その中から正社員2名・パート2名の計4名を採用し、人手不足の危機を見事に脱却。当初2万円を想定していた採用予算も実際は7千円程度で済み、費用面でも大成功となりました。
この事例からわかるのは、オンラインの力を最大限活用することで短期間で優秀な人材に出会えるということです。地方の工業都市で「花屋志望の若者なんて少ないだろう」と思いきや、蓋を開けてみれば想像以上に「花屋で働きたい」人が潜在していたのです。彼らに情報を届ける手段として、ネット求人は非常に有効だったわけですね。
花屋求人のおすすめ戦略まとめ
上記のケースも踏まえつつ、花屋の求人募集を成功させるためにオーナーが取るべきおすすめ戦略を以下にまとめます。
- マルチチャネル戦略で募集範囲を拡大: オンラインとオフラインの両方に求人情報を出し、できるだけ多くの求職者の目に留まるようにしましょう。
一つの方法に頼るのではなく、求人サイト、SNS、自店ホームページ、店頭貼り紙、業界専門サイト、ハローワーク…使えるものはすべて活用するくらいの姿勢が大事です。特にネットに疎い世代とネット中心の若者世代では情報収集経路が違うため、複数経路で発信して母集団を広げることが必要です。 - 求人内容を工夫して魅力を伝える: 応募したくなる求人情報づくりにも力を入れましょう。
ポイントは「このお店で働いてみたい!」とイメージさせることです。例えば仕事内容は単調に書くのではなく、お店の雰囲気ややりがいを感じられる表現を交える、写真や動画を添えて職場の様子を見せるなど工夫します。
募集要項には未経験OKや研修ありなどハードルの低さも明記しましょう。実際、花屋のバイトはほとんどの場合未経験でも応募可能で、働きながら花束の作り方などを身につけていける仕事です。
花が好きで明るく接客できることの方が重視され、専門的な知識は入ってから学べるとされています。ですから、「未経験者歓迎!」と大胆に書いて人材の裾野を広げることが大切です。
応募者に「自分でも挑戦できそう」と思ってもらえる求人情報を心がけましょう。 - 応募者のモチベーションを引き出す工夫: 給与や勤務時間といった条件面はもちろん正直に提示すべきですが、花屋ならではの魅力もアピールしましょう。
例えば「季節ごとのイベント装花に携われます」「社員割引でお花を購入できます」「花の資格取得を応援します」といった付加価値は、他業種にはない魅力です。
また先述の岡田花店さんのように、「経験を積んで技術を身につけたい若手」にとって魅力的な職場であることを発信するのも効果的です。
応募してきた方には面接時にぜひお店の奥で美しく咲く花や、先輩スタッフが生き生きと働く姿を見せてあげてください。花屋で働く楽しさを具体的に想像できれば、入社後のミスマッチ防止にもつながります。 - 柔軟な採用プランを用意する: 人材確保のためには柔軟性も重要です。
たとえば、「どうしても正社員が見つからない…」という場合は、長期パートやアルバイトからスタートしてもらい、ゆくゆく正社員登用を検討する道もあります。あるいは繁忙期だけ短期アルバイトを募集して乗り切るのも一つの方法です。
さらに、専門の派遣会社から人材を紹介してもらう選択肢もあります。花業界に特化した派遣サービスなら必要な時期にすぐ働ける人を手配でき、未経験者でもマッチングしやすい仕組みがあります。
短期的には派遣スタッフで凌ぎつつ、長期的な直接雇用を並行して探すといったハイブリッド戦略も検討しましょう。 - 採用後のフォローと定着: 採用がゴールではなくスタートです。
苦労して採用したスタッフには長く活躍してもらいたいですよね。最初のうちはマンツーマンで丁寧に教える、定期的に面談して不安や要望を聞く、仕事になじむまでは負担の大きい業務を任せすぎない、といった定着のためのフォローも忘れずに行いましょう。
特に未経験で入ったスタッフは最初戸惑うものです。ここでしっかりサポートすれば、「このお店に入ってよかった」と思ってもらえ、結果的に長期的な人材確保につながります。人材育成が次の採用時には「未経験でもちゃんと育ててくれるお店」という評判となり、良い人材が集まりやすくなる好循環も生まれるでしょう。
まとめ:効果的な花屋求人のポイントと今後の展望
花屋の求人募集は昔に比べて難しくなったとはいえ、ポイントを押さえて工夫すれば十分に良い人材と巡り合うことができます。カギとなるのは以下の点です。
- 多方面への情報発信: 「花屋 求人」を必要としている求職者に情報が届くよう、オンライン・オフライン両面からアプローチする。
- 魅力的な職場アピール: 花屋で働く魅力ややりがい、学べることを積極的に発信し、応募者の心を動かす求人内容にする。
- 未経験者を恐れない: 未経験歓迎の姿勢で人材の裾野を広げ、花が好きな人なら一から育てるくらいの気持ちで採用する。
- 柔軟な採用・活用: 正社員・アルバイト・派遣など雇用形態を柔軟に組み合わせ、まずは人材を確保してから育成・定着を図る。
- スピードとタイミング: 募集をかけるタイミング(母の日など繁忙期前は競合も増える)、応募へのレスポンスの早さなども意識し、良い人材を逃さない。
今後も少子高齢化による労働力不足は続くと見られ、花屋業界も人材確保の工夫が求められます。
しかし一方で、「花が好き」「人を笑顔にしたい」という熱意ある若い世代も確実に存在します。
これからの採用では、そうした次世代を惹きつける発信力がポイントになるでしょう。SNSやウェブを駆使してお店の魅力を発信し続けることで、「ぜひここで働きたい」というファン人材を育てていくことも可能です。
花屋の求人は決して楽な道のりではありませんが、お店にマッチした素敵なスタッフに出会えれば、その後の事業運営がぐっと安定し、さらなるサービス向上や売上アップにもつながります。
今回ご紹介した方法や戦略を参考に、ぜひ貴店に合った形で実践してみてください。花と人を繋ぐ素晴らしい仲間を見つけ、共にお店を盛り上げていきましょう!🌸
<参考資料>
- 花屋業界の課題(人手不足・店舗減少)premier-recruit.jp
- 花屋求人の現状と人材不足の背景ciao-parterre.ssl-lolipop.jpciao-parterre.ssl-lolipop.jp
- 求職者の花屋求人の探し方(求人サイト・専門サイト・直接問い合わせ 等)prrr.jpprrr.jp
- 老舗花屋の採用成功事例(オンライン求人活用)airregi.jpairregi.jp
- 花屋の給与水準(低さの例)your-intern.com
- 花屋バイトは未経験でも始められる点premier-recruit.jp
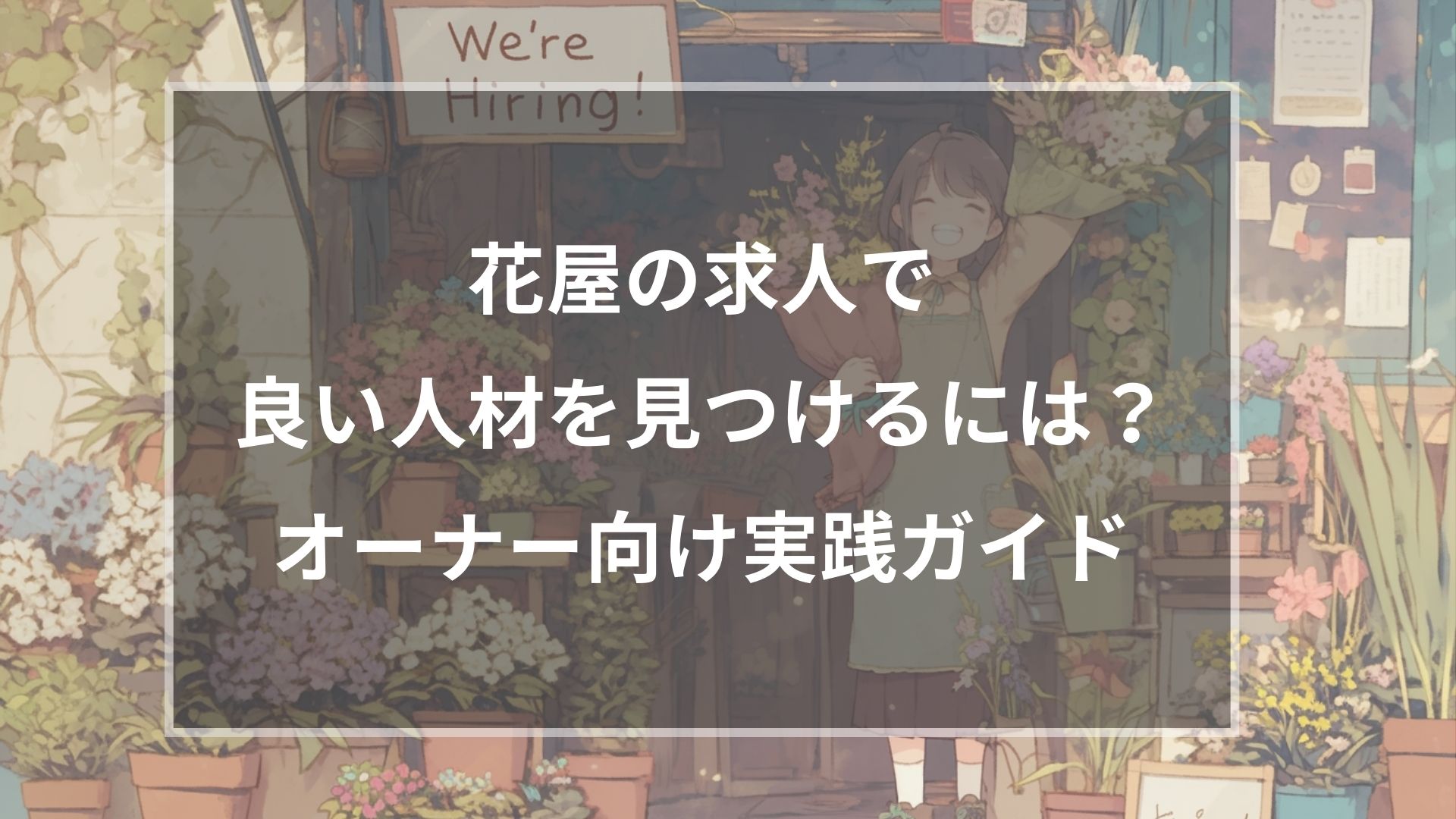
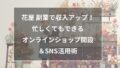
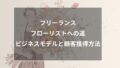
コメント